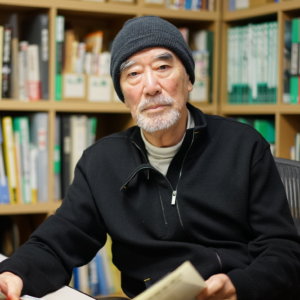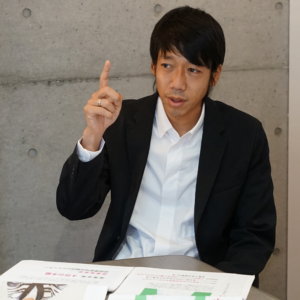早見 和真さん(小説家)
大学時代の思い出は
大学1年のころ、ウチの実家が完全に傾いたんです。「ちょっともう、学費も払ってあげられない。悪いけど実家に帰ってきてくれ」電話越しにうなだれる父の言葉を、そのときすべて拒絶した。仕送りは一切いらない。学費も家賃も、全部、自分で働いて出すから—。親父が調子悪いから行きたい海外にいけないなんてダサい……、そんな感覚だった。それから色々考えだして。バイトして海外にいくのは前提として、その海外をお金に変えたい、と思い始めた。それで、それまで、殆ど日記すら書いたことのないような人間だったけど、唯一、〝おじさんに好かれる〟という自分の特性を生かして、出版社にアポなしで売り込みをかけ始めたんです。でも、20歳の何もない人間が、いきなり「何か書きたいです」と来ても、大抵、門前払いです。それでも、一定数、面白がってくれる粋なおじさんたちもいて、なんとか仕事にありついた。記念すべき初仕事は朝日新聞出版の『アエラ』。当時、「世界の遺産」という企画があって、そのページを任せると言うんです。自分で文章を書いて、写真も撮れるなら撮ってくればいい—、「原稿料はずむよ」と言ってくれて。で、20歳でアエラに載った、となると、やっぱりインパクトがある。名刺代わりにもなるわけですよ。そのうち、海外を周って帰ると、却ってお金が増えてる、なんてことも出てきて……。楽しかったですね。一生、コレでいいな、と思った時期もありました。
卒業、就職の時期が来ます
そんなふうだから、大学には全然行かなくて、一方で、就職活動はしたかった。相変わらず、小説家やノンフィクションライターにはリアリティを抱けないし、いよいよ、新聞記者しかない、と気持ちは固まるばかり……。でも、大学3留の経歴のおかげで、ことごとく書類で落としてくれて(苦笑)。ただ、それでも、面接に行けば間違いなく勝てる、という自信はあった。同年代の誰より経験を積んでいるぞ、とね。結局、8社が面接に呼んでくれて、そのうち7社に内定を貰うことが出来た。ロスジェネ世代なので、これはよく驚かれますね。
作家への転機はいつ
沢山の内定から、最終的に決めたのは朝日新聞社だった。国学院から朝日新聞は十数年ぶりの快挙というので、大学はこれでもかとチヤホヤしてくれる。ところが、これにはよもやの落とし穴があって。海外に入り浸っていたせいで、ろくに単位を取れていなかったんです。ともあれ、「朝日の内定」という快挙に、大学も特例を出してくれるのでは、と淡い期待もしていたんですが……。家の経済状況はいよいよ悪いし、ついに煮詰まって、すべてを朝日の人事部長に打ち明けると、「来年もう一度受けろ。下駄をはかしてやるとは言えないけど、私たちは早見くんのことを忘れないと思う」と言ってくれた。でも、その瞬間、ギリギリで、なんとか張りつめていた糸がプツンと切れてしまって。大学に戻る気力もなく、そもそも学費の用意も出来ず、さあどうしよう、となったとき、人生で初めて家に引き籠った。親も世間も、何もかも恨めしくて、電話も出ずに過ごしたけど、2カ月ぐらい経ったとき、ふと集英社に勤めるある編集者の電話に気付いた。僕の10歳上で、貧乏な僕を面白がって、銀座の店に連れてってくれるような人だった。その電話に出たのは本当にたまたまだった。クサってる僕を心配してかけてくれた気遣いにもほだされて、2カ月ぶりに電車に揺られ、終電で新宿に向かい、飲み始めた。話は、自然、お互いのルーツに及び、僕は原体験の高校野球を話した。すると彼は、僕は小説の編集者だから小説を読んであげるしかできないけど、君が山ほど本を読んできたのはよく分かってるつもりだ。ダメ元で野球の小説を書いてごらん、と提案した。出版の約束はできないけど、読んであげるのは約束する。生活に不便のないよう、アルバイトの口まで世話するから、と—。それを聞いたとき、これが間違いなくラストチャンスだと思った。その翌日、大学に退学届けを出し、書き始めたのがデビュー作の『ひゃくはち』という小説で。そこから運命が転がっていった。
新作『ザ・ロイヤルファミリー』について聞かせてください
競馬はブラッドスポーツと呼ばれ、一般的には血の継承がテーマになりがちですが、僕はそれよりも、馬に託した想いの継承だ、という思いがあって……。それは、僕がデビュー作から一貫して書いてきた親と子、父と息子といったテーマ—今までは表向きは隠して、内包してきたテーマで、いつかそれをメインに書かなきゃなと、密かに温めていたんですが、それとピタッと結びついた。それで、これはちょっと逃げずに、継承をテーマに書きたいな、と。それがはじまりで。
若者にアドバイスを
毎年、高校に講演に行くんです。そういうとき、僕は決まってインド帰りみたいな、少し汚い恰好に、なるたけロン毛で行く。ワケの分かんないあんちゃんが来て、全然小説には触れず、目に見えるものだけに囚われるから現代は息苦しい。もっと目に見えないものにも目を向けないと、と諭す。そして、自分が彼らと同じ年の頃に、大人を見極めようとしていた話をする。そうして、みんなにとって最初の大人がオレだと思うなら、連絡してきて、と話す。そんなやり取りから何かが生まれることを期待している。底にあるのは、高校生が目覚めることにしかこの国の未来はないという思いです。この先、地球環境に何か重大なことが起きたとき、若い人たちは生き残れない。でも、今、世界の舵取りをしてるのは、そんな世界でもどうせ生き残れちゃうオジさんたちです。若者が自分たちの未来を自らの手で切り拓いていって欲しい、そんな切実な願いがいつもあるんですね。
はやみ かずまさ 1977年、神奈川県生まれ。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。2015年『イノセント・デイズ』で第68回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を受賞。『ひゃくはち』『イノセント・デイズ』以外にも、『ぼくたちの家族』『小説王』『ポンチョに夜明けの風はらませて』など多くの作品が映像化されている。他の著書に『95 キュウゴー』『店長がバカすぎて』『神さまたちのいた街で』『かなしきデブ猫ちゃん』(絵本作家かのうかりん氏との共著)、最新作『ザ・ロイヤルファミリー』がある。
(月間MORGEN archives2020)