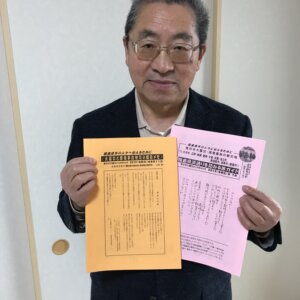塚田 万理奈さん(映画監督)
休日や余暇には、まるでやることが見つからない。以前とうってかわり、今度は暇をつぶすため、少女はまた、せっせと映画館へ足を向けた。そうして一日を映画と映画館で過ごすうち、「今一番好きなことは映画かもしれないなあ」……自然とそんな風に思うようになった。やりたいこともまだ全然はっきりしないけど、今一番傍にあるのは映画に間違いない。それに、映画をつくる人たちに会ったら友達になれるかもしれない……、思いを胸に叩いたのが日大芸術学部、映画学科の門だった。
摂食障害のはてに
希望を抱いて開けた芸術の扉。しかしなにしろ、自信も実績も何もないところからのスタートである。それでも「大学は本当に面白かった」と目を輝かせた。想像した通り、キャンパスには、映画が大好きな若者たち、映画を志す若人の熱気が心地よく満ちていた。様々の人種と楽しく触れ合うなかで、しかし次第に塚田さんはあることに気付いてゆく。「私は嘗められている」。映画学科に入学するほとんどが、その方向を見据え、勉強し、高い自尊心を具えていた。「曖昧な地図しか持たない自分は、下に見られている」――そう思うと、一気に息苦しくなった。

魅力的な同期生たちに囲まれながら、自信を失うばかりの時が流れる……、やがて卒業制作の時期がやってくると、周囲は次々と意気軒昂にフィルムに全身を叩き付けた。それを見た途端、急激な酸欠を感じ、塚田さんはついに窒息した。「私には進むべき道も、撮りたい映画も、誇るべき知識も何もない」。気付いた時には拒食症になっていた。拒食症は思いのほか重かった。母は、はじめ混乱して泣き、父は、困惑の色を見せた。塚田さんは就職活動の中断を余儀なくされる。ある時、尊敬する大学の教師に、「自分には何一つ誇れるところがない。何も撮るものがない」そう訴えた。泣きじゃくる教え子に「じゃあ何もない自分を撮ればいい。何にも格好つけずにありのままを。それが君なんだから」含めるように話す師の言葉は、痛んだ心に静かに浸みていった。