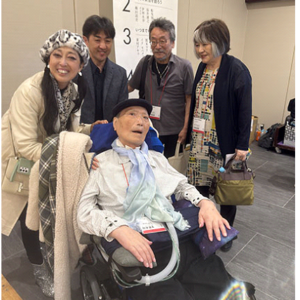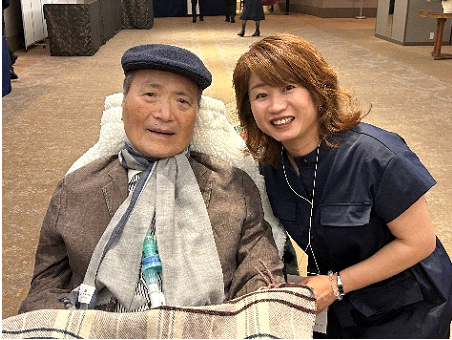
「わたしのマンスリー日記」第23回「ウォーリーをさがせ!」―勇気の波紋
実に見事な感想文です。こんな優秀な先生が小学校教育を支えていることを知って感銘を受けました。先ず私の本をしっかり読み込んで、その上で自分の言葉を紡ぎ出しています。「勇気の波紋。その中心、最初の一滴が谷川先生です」というくだりを読んだときは正直うなりました。
「先輩教師」という言葉も大いに気に入りました。私は社会的には大学教授であり教育学者でしたが、それ以前に自分が一介の「教師」であることを深く心に刻んでいました。だから小学校の先生から「先輩教師」と言われるとこの上なく嬉しいですし、誇りにさえ思います。
教育界ではよく大学等に勤める「研究者」に対して「現場の教師」という言葉が使われてきました。その言い方に私はずっと違和感と不快感を抱いてきました。子どもたちのための教育改革を推進するのに、「研究者」も「現場の教師」もあるものか、とずっと思ってきました。そんな思いでいたので、私は小中学校で数多くの飛び込み授業(実験授業)を試みてきました。なぜそのような活動を続けてきたかについては、別の機会に詳しく書くことにします。
いずれにしても、蔦谷先生の感想文にあるように私は大分大附属小で生活科の授業を敢行したのです。大学の教員による最初の生活科の授業でした。
ウォーリーの授業
平成元(1988)年の学習指導要領の改訂によって、小学校の低学年に「生活」という教科が新設されることになりました。戦後の最初の教科の再編とあって空前の論議を巻き起こしました。低学年社会科・理科を廃して設置されることになったことに加えて、高等学校の「社会科」が「地理歴史科」と「公民科」に再編成されることになったために、とりわけ社会科関係者の間から「社会科解体」として強い反発が起こっていました。
生活科がどのような教科で、私がそれにどうコミットしたかについては『ALS 苦しみの壁を超えて―利他の心で生かされ生かす』に詳しく書きましたのでご覧ください。
生活科は平成4(1992)年度から完全実施することになっていたのですが、前年になっても生活科についての疑念を払拭する状況ではありませんでした。そこで生活科の授業の範を示すために、文部省の生活科担当の視学官だった中野重人(故)先生が実際に授業を公開でやったらどうかという話が持ち上がったのは、平成3(1991)年の秋口のことでした。
中野先生がやってもいいと思っていたようですが、私たち取り巻きは自制するよう進言しました。賛否両論渦巻く中、文部省の担当官が直接授業をするのはリスクが高いと判断したからです。授業が成功裏に終われば問題はないのですが、そうでなかった場合は生活科に批判的な陣営から「それ見たことか」と言われることが誰の目にも明らかでした。
ならば自分がやってやろうと私は心に決めました。理由は単純でした。たとえ失敗しても「所詮大学の先生がやっても駄目だよな」と笑われるのが落ちでした。今考えると大変な決断をしたものだと思います。小学校での教師経験のない大学の教員が生活科の先行きに影響を与えるかもしれない実験授業に挑戦するというのですから、話題にならないはずがありません。