
対話的探究への招待――哲学すること、対話すること
ギリシア語の原語(philosophia)は「知」(sophia)と「愛」(philia)という言葉が組み合わされたものですから、これらはほぼ直訳といってよいでしょう。「哲学」の原義は、「真理の奥底を極めなければやまぬ」、「あくまで知ろう」とする徹底した探究にあるのです6。その原動力となるもの、それが「知への愛」です。
たとえばプラトンの『ゴルギアス』では、ソクラテスは対話的探究の相手、カリクレスに次のように語りかけます。
「そこで、友情の神ゼウスの名にかけて、カリクレスよ、どうか、君自身としても、ぼくにに対して冗談半分の態度をとるべきではないと考えてくれたまえ。また、その場その場の思いつきを、心にもないのに、答えるようなこともしないでくれ。さらにまた、ぼくのほうから話すことも、冗談のつもりで受け取ってもらっては困るのだ。なぜなら、君も見ているとおり、いまぼくたちが論じ合っている事柄(ロゴス)というのは、ほんの少しでも分別(ヌース)のある人間ならばだれであろうと、そのこと以上にもっと真剣になれることが、ほかにいったいなにがあろうか、といってもよいほどの事柄なのだからね。7
対話的探究においては、このような仕方で、「対話」と「哲学」が結合されます。真理は、他者と共有可能なものであり、またそうでなくてはなりません。それゆえ「哲学」という営みは、「対話」を要請します。そして「対話」は、それが真剣なものであるかぎり、徹底した探究の態度を求めます。対話的探究においては、「対話」と「哲学」が組み合わされ、双方の精神がいかんなく発揮されるのです。
以上のような理解に基づいて、本連載は「対話的探究への招待――哲学すること、対話すること」と題されています。連載は3部から構成されます。第1部では、「哲学」と「対話」という二つの営みの輪郭を描きます。そのうえで両者の関係を問い、「対話的探究」という営みを浮かびあがらせます。第2部では、プラトンのいくつかの対話篇を読み、「対話的探究」の理解を深めます。『ラケス』という対話篇では、ソクラテスのファシリテーションについて学ぶことになるでしょう。第3部では、哲学カフェと死生学カフェを中心に、筆者による対話的探究の実践を紹介します。そのうえで読者が対話的探究に着手できるように、問いの設定やファシリテーション、場づくりなどの具体的な指針を示します。
次回は「哲学」という営みについて、さらに掘り下げた考察を試みます。どうぞお楽しみに。
6 田中美智太郎『哲学初歩』岩波書店、1950年、14-15頁
7 プラトン「ゴルギアス」加来彰俊訳、『プラトン全集9』所収、岩波書店、1974年、
165-6頁(500b5-c4)
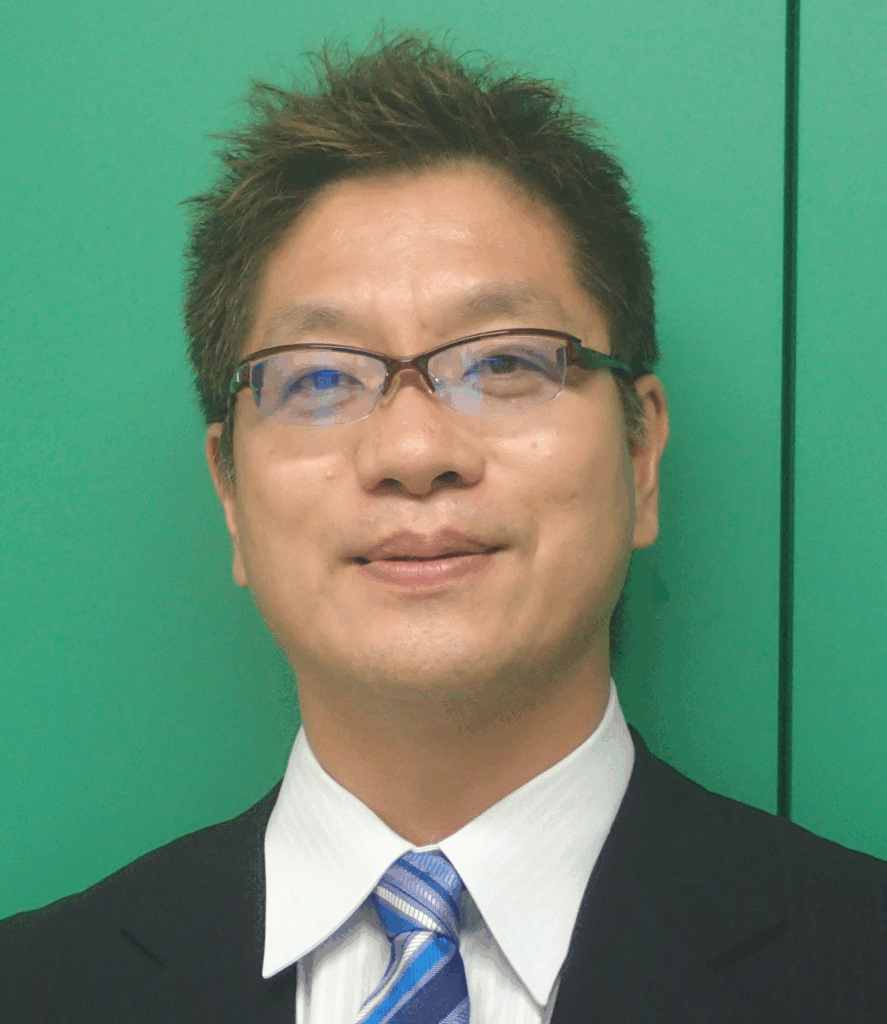
竹之内 裕文(たけのうち・ひろぶみ)
静岡大学未来社会デザイン機構副機構長、農学部・創造科学大学院教授。専門分野は哲学・死生学。東北大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(文学)。東北大学大学院文学研究科助手、静岡大学農学部・創造科学技術大学院准教授を経て、2010年4月より現職。ボロース大学(スウェーデン)健康科学部客員教授(2011-12年)、グラスゴー大学(英国)学際学部客員教授(2022年)、松崎町まちづくりアドバイザー(2022年-現在)。
「対話」と「コンパッション」を柱に、国内外で広く活躍している。死生学カフェ、哲学塾、風待ちカフェ、対話・ファシリテーション塾などを主宰する。団体コンパッション&ダイアローグ(一般社団法人化を予定)代表。『死とともに生きることを学ぶ 死すべきものたちの哲学』(ポラーノ出版)により第14回日本医学哲学・倫理学会賞を、研究発表「『死』は共有可能か? ハイデガーと和辻との対話」により第8回ハイデガー・フォーラム渡邉二郎賞を受賞。
(モルゲンWEB 20250421)

