
対話的探究への招待――哲学すること、対話すること 第1部 哲学と対話
このような態度にとどまるひとを、カントは「生徒」と呼びました24。生徒に欠けているもの、それは著者の問いを引き受けて、みずからの理性を行使して探究する、つまり身をもって哲学するという態度です。哲学は、みずからの身心を使って取り組む「実技」なのです25。
わたしたちは、過去の哲学者が提起した問いを引き受けるだけでなく、みずから問いを立てて、哲学することができます。じっさい日常生活において、ふとした違和感や疑問を抱くことがあるでしょう。ただほとんどの場合、それらは「問い」にまで育て上げられることなく手放され、忘れ去られてしまいます。目の前の事物や現象に呼びとめられて、あるいは他者と出会い、対話することを通して、わたしたちは問いを育てることができます。問いを立て、相手と共有すれば、共に探究を進めることができます。「共に哲学する」ことが可能になるのです。それによって哲学の営みは、よりいっそう豊かなものになります。
「共に哲学する」という生の実践と捉えられるとき、「哲学」は「何か確定した学問や研究成果を示すものではなく、むしろ未来へ向けて現在進行中の、英語で言うオンゴーイング・プロジェクト」となります26。このプロジェクトを成功させるためには、開かれた対話のプラットフォームを築き、多様な背景をもつ人びとの参画を促す必要があります。居住地域や性別、人種、国籍、使用言語、文化・宗教の差異を越えて、同時に、これらの差異を尊重しながら、共に哲学するのです。
「哲学」は確定され固定されたものではありません。むしろ動態的で、開かれたもの、それゆえに携わる者に安住を許さない生の実践です。このような理解を携えて、自由で、明るい、哲学の「大道」を歩むことにしましょう。
わたしたちは与えられた公式や図式に、無理やりわたしたちの思考をあてはめようとして、思想の難解を歎なげいたりするけれども、そのようなものは思想でもなければ、哲学でもないのである。ギリシア以来の本物の哲学者が、歩いてきた大道について見るならば、哲学の思想はもっと自由で、明るいものであることが知られるだろう27。
筆者はいまだ「賢徳」に達していません。なお探究の途上にあります。だからこそ「賢徳」を希い、共に哲学することを試みます。このような自覚を携えて、本連載の第二部では、ソクラテスとプラトンの愛知の営みへ立ち返ります。
24『カント全集6』有福孝岳・久呉高之訳、岩波書店、2006 年、115-116 頁。なおここで「生徒」と訳された独語(Lehrling)は、「徒弟」や「見習い」と訳すこともできます。
25 野矢茂樹『哲学な日々 考えさせない時代に抗して』講談社、2015年、16-7頁。
26 納富信留『世界哲学のすすめ』ちくま新書、2024年、36頁。
27 前掲『哲学初歩』vii頁。
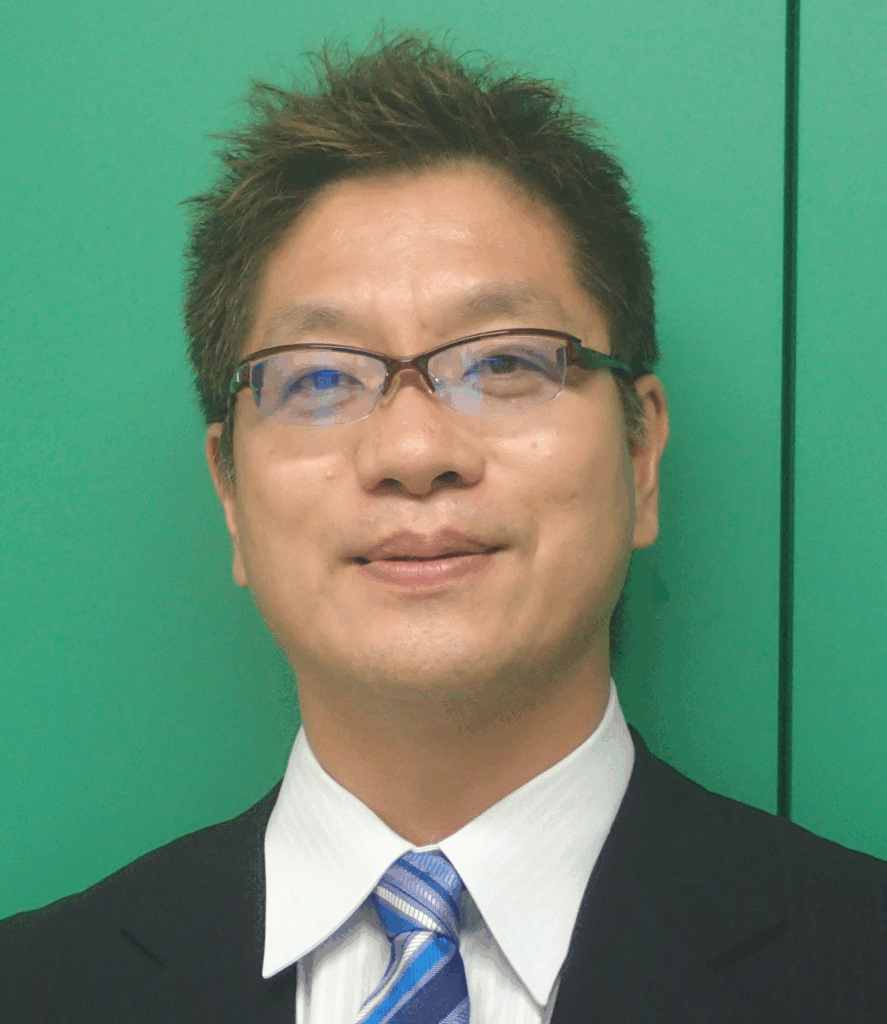
竹之内 裕文(たけのうち・ひろぶみ)
静岡大学未来社会デザイン機構副機構長、農学部・創造科学大学院教授。専門分野は哲学・死生学。東北大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(文学)。東北大学大学院文学研究科助手、静岡大学農学部・創造科学技術大学院准教授を経て、2010年4月より現職。ボロース大学(スウェーデン)健康科学部客員教授(2011-12年)、グラスゴー大学(英国)学際学部客員教授(2022年)、松崎町まちづくりアドバイザー(2022年-現在)。 「対話」と「コンパッション」を柱に、国内外で広く活躍している。死生学カフェ、哲学塾、風待ちカフェ、対話・ファシリテーション塾などを主宰する。団体コンパッション&ダイアローグ(一般社団法人化を予定)代表。『死とともに生きることを学ぶ 死すべきものたちの哲学』(ポラーノ出版)により第14回日本医学哲学・倫理学会賞を、研究発表「『死』は共有可能か? ハイデガーと和辻との対話」により第8回ハイデガー・フォーラム渡邉二郎賞を受賞。
(モルゲンWEB20250611)

