
対話的探究への招待――哲学すること、対話すること 第1部 哲学と対話
◆ 日本社会で対話を実践する
福島原発事故は、日本の近代化の歩みにおけるひとつの帰結であるように思われました。このような視点から近代日本の歩みを辿りなおしていたところ、筆者は福沢諭吉『文明論之概略』(1875年)の次の一節と出会いました。
[現在の日本人は]天然の禍福(かふく)を待つように、ただ黙座して事の成り行きをみだけだ。実に怪しむべきことではないだろうか。かりに西洋諸国においてこのたぐいの事件が起こったら、その世論はいったいどうなるだろうか。衆口(しゅうこう)が湧くように、一時の舌戦が開かれて大騒動となるはずだ。(略)ただ日本人[だけ]が無議の習慣に制せられて、安んじていられないのに穏便(おんびん)に安んじ、開くべき口を開かず、発すべき議論を発しないのは驚くばかりだ。5
「無議の習慣」(議論を尽くさない習慣)は習慣だから変えられる。福沢がそのように説いてから、150年が経ちます。現在のわたしたちは、「無議の習慣」を改めたでしょうか。たしかに黙って事の成り行きを見守るのでなく、開くべき口を開き、発すべき議論を発するようにはなったようです。先に確認した通り、原発事故後にも、多くの議論がありました。しかし、成熟した議論にはなお到達していないようです。スウェーデンで「対話」と出会うことで、それが明らかになりました。現在の日本社会でくり広げられる論議・議論に欠けているもの、それは共通の問いのもとで、異なった意見に注意深く耳を傾けるという対話の流儀です。これらを欠くと、せっかくの議論も豊かな実りをもたらしません。
問いが共有されるところでは、参加者は異なった立脚点と視点から、これに回答を試みることになります。共通の事象に対して異なった視角からアプローチされることで、事態が立体的に浮かび上がります。それによって多様な知恵が結集されます。しかし共通の問いを欠くと、議論は各個の意見の応酬という様相を呈します。さらに相手の意見に関心が寄せられず、耳が傾けられないと、他者のアイデアが顧みられません。ときには封殺されてしまいます。その結果、各人は自説をひたすら押し通すことになります。それでは事柄の理解は深まりません。
成熟した議論を展開するためには、「問い」が共有され、相手の言葉に「聴く」ことが求められます。それとともに「対話」という共同の探究が可能になります。
現在の日本社会が必要とするもの、それは「対話」である。この確信に導かれて、筆者は帰国後、本格的な対話実践に着手します。2012年には大学内で「生命環境倫理学フォーラム」を立ち上げ、原発、持続可能性、格差社会、生活保障、食料危機、貨幣などのテーマについて、学生や市民と対話を試みます。2013年には拠点を市街地へ移し、哲学カフェを始めます。さらに2015年には死生学カフェを創設します。これらの経験を重ねることで、「対話」の定義がさらに深化していきます。それについては、本連載第3部「対話的探究の実践」で紹介します。
5 福沢諭吉『文明論之概略』岩波文庫、1995年、117-8頁。ただし読みやすいように、表記に手を加えてあります。
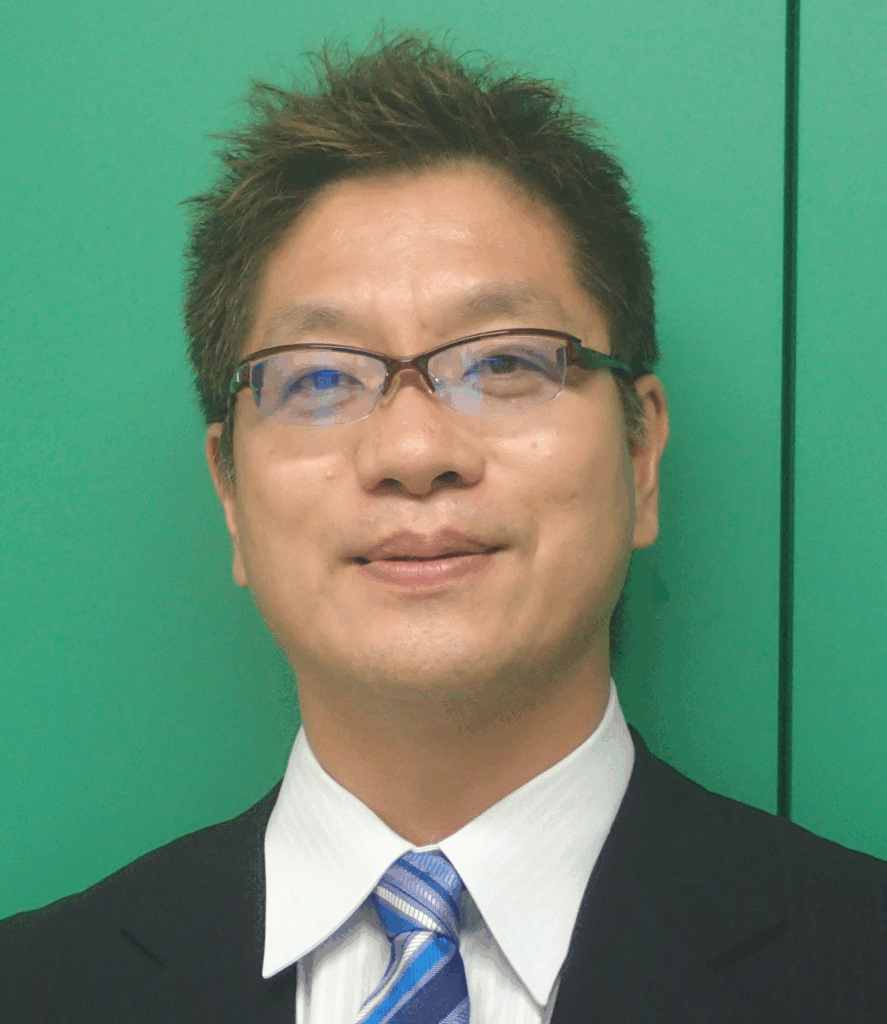
竹之内 裕文(たけのうち・ひろぶみ)
静岡大学未来社会デザイン機構副機構長、農学部・創造科学大学院教授。専門分野は哲学・死生学。東北大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(文学)。東北大学大学院文学研究科助手、静岡大学農学部・創造科学技術大学院准教授を経て、2010年4月より現職。ボロース大学(スウェーデン)健康科学部客員教授(2011-12年)、グラスゴー大学(英国)学際学部客員教授(2022年)、松崎町まちづくりアドバイザー(2022年-現在)。
「対話」と「コンパッション」を柱に、国内外で広く活躍している。死生学カフェ、哲学塾、風待ちカフェ、対話・ファシリテーション塾などを主宰する。団体コンパッション&ダイアローグ(一般社団法人化を予定)代表。『死とともに生きることを学ぶ 死すべきものたちの哲学』(ポラーノ出版)により第14回日本医学哲学・倫理学会賞を、研究発表「『死』は共有可能か? ハイデガーと和辻との対話」により第8回ハイデガー・フォーラム渡邉二郎賞を受賞。
(モルゲンWEB20250627)

