
対話的探究への招待――哲学すること、対話すること 第1部 哲学と対話
「議論」と「討論」を「対話」と対比しておきましょう。「議論」では、最善の結論に共に到達するという目的のもと互いが発言し、それを通して思考・探究のプロセスが共有されます。議論では、対話と同様に、「相手をパートナーとして」、「相手の言葉を受けて話す」ことが実践されるのです。また最善の結論に到達するためには、様々な考えが自由闊達に表明されることが奨励されます。それに応じて議論では、「対等」ということにも重きが置かれるでしょう。しかし議論においては、「相手と正面から向き合う」ことは重要ではありません。最善の結論へ導く意見こそがよい意見なのであって、だれが、どのような背景から、それを発言するかは、基本的に問題とされないのです。さらに議論と対話の違いは、「最善の結論に到達する」という目的そのものにも見られます。最善の結論に到達できない議論は失敗と見なされるでしょう。しかし対話では、なんらかの結論に達することがそもそも求められていません。対話的探究の場合も同様です。対話的探究とは、問いが共有される言語的コミュニケーションです。問いをわかちあい、共に探究を進めるというプロセスに主眼があるのであって、問いの解答を得ることが目的ではありません。かりに明確な結論に到達できなかったとしても、それによってただちに対話的探究が失敗と見なされるわけではありません。
「討論」になると、対話との相違はさらに大きくなります。ひとつには、討論には、相手と「正面から向き合いながら、相手の言葉を受けて話す」という態度が欠けています。たしかに論敵としての相手に「正面から向かい合う」ことはあるでしょう。しかし、人格的な交流を深めるということは、まず起こりません。もうひとつには、「相手の言葉を受けて話す」ためには、相手の語りを聴く必要があります。しかし討論では、相手の論を討ち負かすことに主眼が置かれるため、往々にして、聴いて考えるという営みが素通りされます。相手の論を討ち負かしたのでは、対話になりません。
以上のように、対話は会話、議論、討論から区別されます。ただ日常的なコミュニケーションでは、会話から対話が生まれ、対話の合間に議論が挿入され、議論が討論へ移り変わることがあります。これら異種の言語的コミュニケーションのあいだを、わたしたちは行ったり来たりします。たとえば共通の話題について会話しているうちに問いが提起され、それがわかちあわれて対話が始まる。対話を進めるうちに、特定の論点に関する議論が立ち上がる。議論がヒートアップし、自分の意見こそが正しいという思いこみが前面に出ると、互いに聴くという態度が失われ、もっぱら討論がくり広げられる。討論によって関係が悪化し、修復の必要が感じられると、改めて共通する話題が出され、ふたたび会話が始まる。筆者も学生時代に夜を徹して、仲間たちと飲み明かしたときなど、このような言語的コミュニケーションの変転を何度か経験しました。
まとめとして、「対話」と「対話的探究」の定義を確認しておきましょう。「対話」とは、「パートナーとして、相手と正面から向き合いながら、対等な立場で、相手の言葉を受けて話す」ことをいいます。対話は「パートナー」「対面」「対等」「応答」という 4 つの要素から構成されます。
問いが共有されると「探究」の要素が加わり、対話は「対話的探究」に姿を変えます。ひとつの問いの前に共に立ち、答えを手にしていないという対等な立場で、言葉のやりとりを通して、共同で探究が進められます。対話的探究は「探究」「パートナー」「対面」「対等」「応答」という5つの要素から構成されます。それを踏まえて、最後に「対話的探究」の定義を示しておきましょう。「対話的探究」とは、「共通の問いの前に立ち、探究のパートナーとして相手と向き合いながら、対等な立場で、相手の言葉を受けて話す」営みです。
次回は、「対話」と「哲学」の関係に光を投げかけ、そこから「対話的探究」の姿を浮かび上がらせることにしましょう。
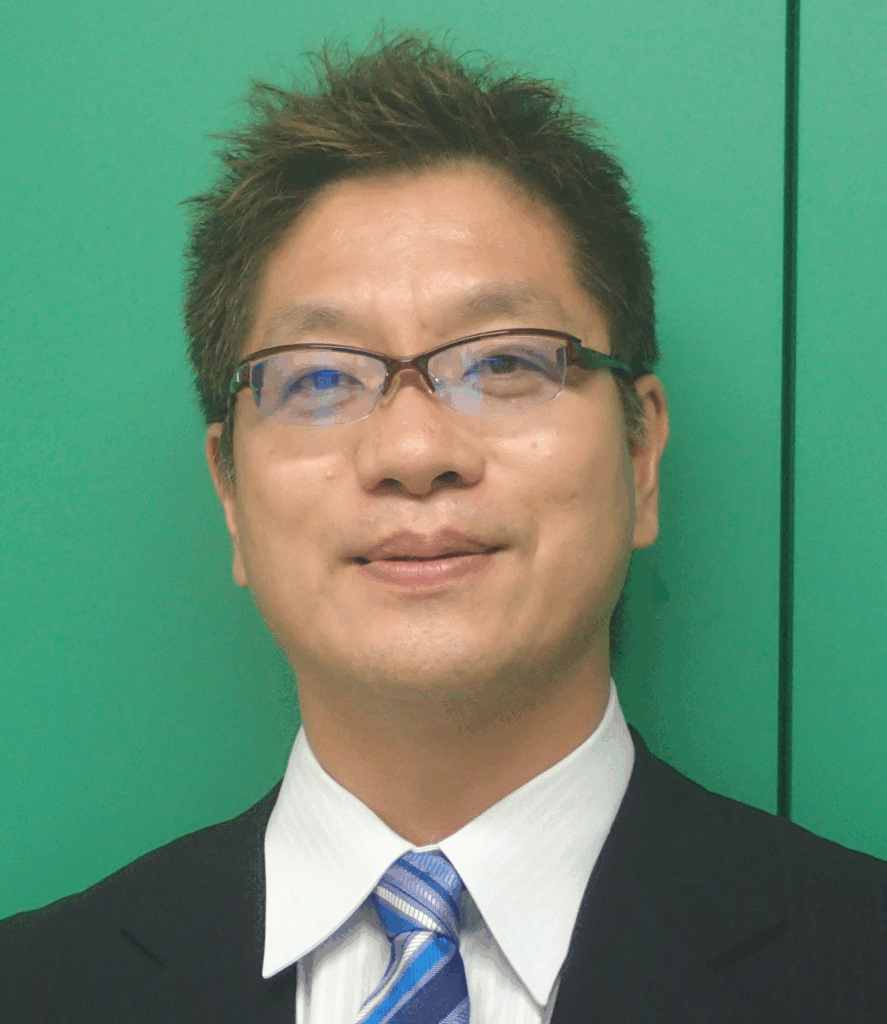
竹之内 裕文(たけのうち・ひろぶみ)
静岡大学未来社会デザイン機構副機構長、農学部・創造科学大学院教授。専門分野は哲学・死生学。東北大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(文学)。東北大学大学院文学研究科助手、静岡大学農学部・創造科学技術大学院准教授を経て、2010年4月より現職。ボロース大学(スウェーデン)健康科学部客員教授(2011-12年)、グラスゴー大学(英国)学際学部客員教授(2022年)、松崎町まちづくりアドバイザー(2022年-現在)。
「対話」と「コンパッション」を柱に、国内外で広く活躍している。死生学カフェ、哲学塾、風待ちカフェ、対話・ファシリテーション塾などを主宰する。団体コンパッション&ダイアローグ(一般社団法人化を予定)代表。『死とともに生きることを学ぶ 死すべきものたちの哲学』(ポラーノ出版)により第14回日本医学哲学・倫理学会賞を、研究発表「『死』は共有可能か? ハイデガーと和辻との対話」により第8回ハイデガー・フォーラム渡邉二郎賞を受賞。
(モルゲンWEB20250724)

