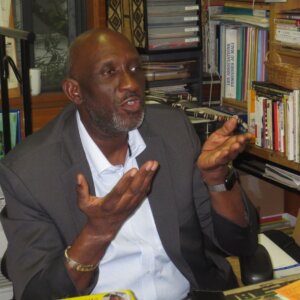石井 光太さん(ノンフィクション作家)
努力を続けるのは難しいことだったと思います
そうですね、ただ僕は幼い頃から、父をはじめ周りのクリエイターの努力を見てきていたので。成功している人、良い仕事を継続している人たちは、みんなそれだけの下地をしっかり作っているのを知っていたんです。”環境に恵まれた″という意味では、そういうものを直に見てこれたことが一番の宝物ですね。
努力をすれば作家になれる確信はありましたか
ありました。もちろん、なれないという怖さは常に抱えていましたけどね。でも、やって失敗することはあっても、やらずに成功することはありませんから、必然的にやるという選択になりますよね。すべてに通じますが、とにかくやらなければスタートラインにも立てないんですよ。
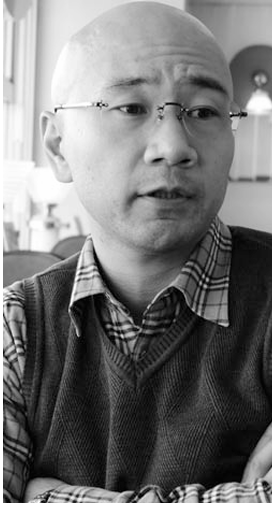
ノンフィクションを志向されたのはいつごろから
高校時代に辺見庸さんの『もの食う人びと』を読んでそこからですね。小説の文体で表現するノンフィクションに目から鱗が落ちて一気に引き込まれて。それまでノンフィクションと言えば、”とにかくジャーナリズム一辺倒の文章表現に重きを置かないジャンル”という思い込みがあったんです。それが、”ノンフィクションも文芸であり文章で勝負できる世界”と知れたのは嬉しい驚きでしたね。そのときに、自分の海外を巡った経験をノンフィクションで書くのがいいのかも、とも考えたりして──。その気持ちが固まったのは、大学の最初の海外渡航先のアフガニスタンです。難民キャンプで苦しむ障害者の方たちを目にしたときに、「これは絶対に伝えなければいけない」と心が奮い立って。
社会問題に関わる作品群を多く書かれていますが着想どこから
自分の惹かれる世界を書いていたら自然とそうなったという感じですね。もともとがジャーナリズム畑の人間ではないので、僕の中で本当に無視できないことを書いているだけなんですよ。アフガニスタンで見たことを僕は到底見て見ぬ振りはできなかったし、そういうものが他の作品にも広がっていったんです。その思いは大学卒業を迎えた頃から変わらなくて、ジャーナリストではなく、あくまでなるたいのは作家だったので、就職にも特に意味を見出せなかったんですね。それに”海外のルポを書けば必ずうまくいく”という確信もあって、そういう意味では「これだ!」というテーマと、「作家になりたい」という信念を早いうちに明確に持っていたのが大きかったと思います。