
「対話的探究への招待――哲学すること、対話すること」第1部 哲学と対話
故人との対話は可能か?
葬儀や墓参に際して、わたしたちはしばしば故人に語りかけます。毎朝、仏壇の前で、故人に思いを馳せ、話しかけるひとも少なくないでしょう。生前に故人が発した言葉が脳裏から離れず、その言葉を反芻し続けているひともいるかもしれません。生活のなかで、あるいは夢のなかで、故人から思わぬメッセージを受けとることもあります。
このようなとき、わたしたちは故人と対話しているのでしょうか。それとも自分の考えを故人に投影させて、自己と対話しているにすぎないのでしょうか。「対話」の定義に立ち返り、5つの構成要素を順に検討することにしましょう。
① 相手をパートナーとして
対話とは、言葉のやりとりを通した協働作業です。対話の相手はパートナーと位置づけられます。対話のありようは、相手とのパートナーシップに応じて変わります。
故人は対話のパートナーとなるのでしょうか。故人とのあいだに、パート―ナシップは成立するのでしょうか。もし生前にパート―ナシップが結ばれていれば、それは死後も、かたちを変えながら継続する、と考えられます。死別と同時に、パート―ナシップが完全に解消される、絆が突如として断ち切られるという考え方は、むしろ暴力的に響きます。
今、ここで、故人と共有したいと願う課題や苦悩、問いがあり、その共有が試みられるならば、故人は引き続き、対話のパートナーとなりうるでしょう。じっさい大きな困難に直面し、どうしたものかと途方に暮れるとき、わたしたちはしばしば、「あなただったらどう考える?」と、故人に問いかけます。
② 相手と向き合って
ここでは「向き合う」ないし「対面」の意味合いが問題になります。前回確認したように、『日本国語大辞典』1では、「対話」が「直接に向かい合って互いに話しすること」と定義されます1。相手は今、ここにいませんから、同一の空間に身をおいて対面することはできません。この定義に従うかぎり、故人と「直接に向かい合」うことは不可能に思われます。
ここで立ちどまって、考えてみましょう。対話において相手と向き合うとは、いったいどういうことなのでしょうか。たとえばレストランで、あなたは深刻な悩みを打ち明けられているとします。そのとき相手の口もとの汚れに目を奪われ、うわの空のまま、話半分で聞いているとしたら、それで相手と向き合ったことになるでしょうか。もちろん物理的には向き合っているといえるでしょう。口もとを注視しているのですから、相手と正対しているはずです。しかし対話のパートナーとして、相手と向き合っているとはいえないはずです。なにしろ相手の言葉を受けとめていない、つまり聴いていないのですから。対話のパートナーとして相手と向き合うということは、たんに物理的に向き合うことを意味しないのです。
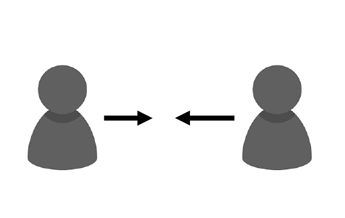
1『日本国語大辞典 第12巻』日本国語大辞典刊行会、小学館、1974年、649頁。

