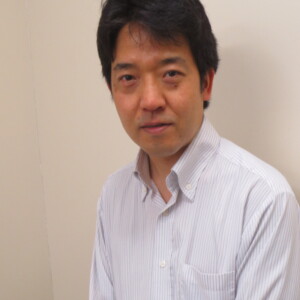【特集】「不登校を考える」大越俊夫さん×中村俊さん
不登校――年間30日を病気、貧困以外の事情で欠席する生徒を指す言葉だ。日本では97年以降、小中学校併せて毎年10万人あまりの不登校児が居場所を求め身を縮めている。世界でも稀なこの一大社会病理に、教育現場に43年間、7500人の不登校児と向き合ったフリースクール『師友塾』塾長・大越俊夫さんと、脳科学と感情教育を専門とする東京農工大学名誉教授・中村俊さんが切り込んだ。
大越俊夫:私はこれまでの教育者生活で、〈元気は正義〉を胸に、子どもの命だけを見つめてきました。普通の学校教育では、勉強さえできればいい――こう言う。でも現場で子どもたちに目を凝らすと、どうも命が薄くなってきているんです。これはなぜだろう、と。ずっと見ていくと、最初、生徒個人の病理からはじまって、家族の問題、そして学校にも問題がありました。メディアは不登校をこの3者間の問題として責め立てましたが、私には、もっと根本的な、戦後日本の社会病理そのもののように感じられました。
中村俊:私は、学問の道に入った動機が生命なので、教育現場に立ち、命に着眼するというのはすごく共感できますね。物質から物質でない命が生まれる不思議――そういうプロセスの中で意識が生まれ、言葉とか精神というものが生まれてくる……それをサイエンスの問題としてやるにはどうするか、というのが私のテーマです。これを軸に、子どもの発達を考えると、命ということを根幹に据えない限り、決して見えてこないだろうと思いますね。

大越:私が命を意識するようになったのは、18歳の時に肺がんになり、入院したことが大きく影響しているんです。その病院では亡くなった利用者のお骨を残る患者たちが箸でとる、というのが決まりで。昨日今日、将棋や囲碁を指したおじいちゃん、おばあちゃんの骨を拾うことになった。この経験は、概念として命を学ぶ以前に、強くその存在を私の心に刻み付けたんですね。命の不思議さと、一方で入院時、ずっと感じていた社会からの疎外感――この二つが私の中でずっと不登校と重なってきたんです。不登校はまず社会から疎外されます。そして復学を願う家族からも疎外される……。そうなるともう本人は部屋に引きこもるしかない。そうして社会に、家族に絶望した子どもが私の前に現れる。