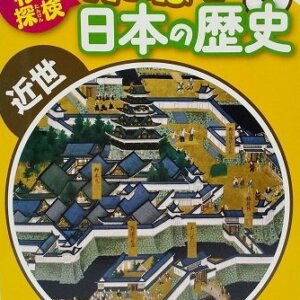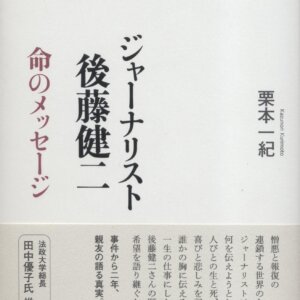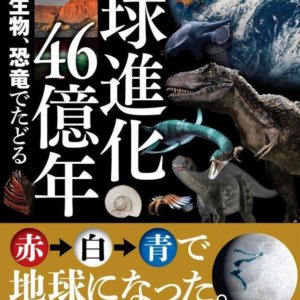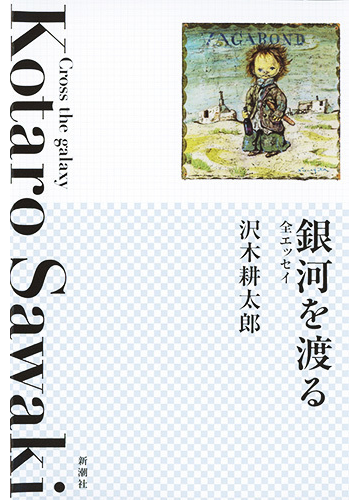
『銀河を渡る』
沢木 耕太郎/著
新潮社/刊
本体1,800円(税別)
君は何者かになりうるんだよ
私たちはエッセイというものに何を求めるのだろうか。自分の青年期の頃を考えると、そこには筆者の個人的な体験や感想、思考から何かを得たい、吸収したい、役立てたいという思いが強かったように思う。
青年期をはるかに過ぎた今になってみると、何かを得たいということより、自分と筆者との重なりや違いを味わう行為に変わってきている。書かれたことと自分に違いが多くても、何かに役立つことがなくともそれで良いのである。ただ、そう言いながらも、「学校」や「教師」といった言葉が出てくると、つい読み方にも力が入ってしまう。
この本の中には、別々の場面で二人の教師が登場する。日比谷高校を希望する筆者に教師たちが「ワンランク落とした方が」と勧める中、断固「自分の好きなようにしなさい」と促してくれた担任の女性教師。大学ゼミの選抜で落とされ、意を決して自宅まで訪問した筆者に「私のゼミに入ってくれますか?」と告げた大学教師。私には筆者のような体験はまったくない。高校受験の面談で「無理そうだ」という担任に、心の中で「これはあなたの人生ではない」と開き直った部類だ。
ただ、全く違う体験しかなかったとしても、それぞれの体験を辿った先でまったく同じ思いに到達することもある。私は、筆者の以下の最後の言葉は多くの学校関係者が全面的に共感するものではないかと思う。
〈そして、こうも思う。教師が教え子に、あるいは「大人」が「若者」に、真に与えられるものがあるとすれば、それは「君は何者かになりうるんだよ」というメッセージだけではないだろうかと……〉
(評・広尾学園中学高校 副校長 金子暁)
(月刊MORGEN archives2018)